この記事を読んでほしい人
- 「ミステリの主要ジャンル」についてある程度知っておきたい人
- 「ミステリの主要ジャンル」には、どんなものがあるのか気になる人
- 「推理小説」を読んでみたいと思ったり、映像作品を見たいと思った人
- 「ミステリの主要ジャンル」についてあまり詳しく知らない人
- 「ミステリー」や「推理小説」が大好きな人
- 「ミステリの主要ジャンル」の代表的な作家や、その作品などを調べてみたい人
ミステリーへのお誘い

新しいミステリの主要ジャンルが出てくる可能性もあるかも

おススメの電子書籍専用リーダー
Kindle(電子書籍)

「kindleストア」は、「Amazon」が運営する「総合電子書籍ストア」で、取り扱っている書籍の数は、他の電子書籍の販売サイトを圧倒的に上回る業界最高クラスであり「全ジャンル」に強く、中でも「ビジネス書」のジャンルが強みがあること、そして「検索性」に優れることや、30日間無料の「お試し期間」もあるなど、使い勝手も抜群!
電子書籍専用のリーダー端末「Kindle」は、紙の書籍に近い読み心地を実現しており使って損はないアイテムですし、また「Amazonプライム」に会員登録していると約1000冊程の書籍が無料で読め、さらに「定額読み放題サービス」である「kindle unlimited」の会員になると、120万冊以上もの本を好きなだけ読むことができるのも魅力的!
「本をたくさん読みたい人」「電子書籍専用リーダー端末『Kindle』を使いたい人」「Amazonの通販をよく利用している人」「読みたい本や欲しい本が決まっている人」「定額読み放題のKindle Unlimitedにとても魅力を感じる人」「ビジネス書を中心に本を購入したい人」には、特におススメ!
Kobo(電子書籍)

「楽天Kobo」は、「楽天」が運営する、「Kindleストア」に次ぐ業界シェアNo.2の安心安全な「電子書籍ストア」で、ジャンルや品揃えに関してはこの2つが業界最高レベルであり、ほとんどすべての「出版社」「ジャンル」の書籍と取り揃えていますが、特に「洋書」に関しては「kindleストア」をしのぐほどの品揃えで使い勝手もよく、また、専用リーダー「Kobo」も高機能で、使って損はないでしょう。
自分の好きな本だけを読むのなら、「ポイント」が使える「楽天kobo」の方が「kindleストア」よりもお得であり、「amazon」より「楽天」を使うことが多ければ、「楽天カード」などとの連携で「ポイント」がザクザク貯まるので、「キャンペーン」や「クーポン」「セール」などをうまく利用し、「ポイント」とあわせて使えば、かなり「おトク」にできますし、雑誌専門の「定額読み放題サービス」である「楽天マガジン」もあるのは魅力!
「楽天市場や楽天関連のサービスを普段よく利用する人」「楽天カードを持っている人」「割引きよりもポイント還元が好きな人」「電子書籍専用リーダー『Kobo』を使いたい人」「小説や洋書を中心に購入する予定の人」「楽天の『セール』や『キャンペーン』『クーポン』を利用したい人」「雑誌だけ読めればいいので『楽天マガジン』に魅力を感じる人」には、とくにおススメ!
【関連記事】
■本格ミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
■【アーサー・コナン・ドイル】
■【アガサ・クリスティ】
■【G・K・チェスタトン】
■【ジョイス・ポーター】
■【F・W・クロフツ】
■【バロネス・オルツィ】
■【イーデン・フィルポッツ】
■【ドロシー・L・セイヤーズ】
◆アメリカ
■【エラリー・クイーン(バーナビー・ロス)】
■【ヴァン・ダイン】
■【ディクスン・カー(カーター・ディクスン)】
■【レックス・スタウト】
■【エドガー・アラン・ポー】
◆フランス
◆日本
■【江戸川乱歩】
■【横溝正史】
■【高木彬光】
■【大下宇陀児】
■【小栗虫太郎】
■【甲賀三郎】
■【大阪圭吉】
■【蒼井雄】
■【濱尾四郎】
■【鮎川哲也】
■【泡坂妻夫】
■【仁木悦子】
■【笹沢左保】
■【島田荘司】
■【笠井潔】
■新本格ミステリー

【代表的作家】
◆日本
■【綾辻行人】
■【有栖川有栖】
■【法月綸太郎】
■【我孫子武丸】
■【折原一】
■【北村薫】
■【芦辺拓】
■【歌野晶午】
■【二階堂黎人】
■【若竹七海】
■【麻耶雄嵩】
■【山口雅也】
■【京極夏彦】
■【倉知淳】
■【愛川晶】
■【霞流一】
■【西澤保彦】
■【柄刀一】
■【北森鴻】
■【森博嗣】
■【高田崇史】
■【舞城王太郎】
■【西尾維新】
■【東野圭吾】
■【米澤穂信】
■ハードボイルド

【代表的作家】
◆アメリカ
■【レイモンド・チャンドラー】
■【ダシール・ハメット】
■【ミッキー・スピレイン】
■【ロス・マクドナルド】
■【ローバート・B・パーカー】
■社会派ミステリー

【代表的作家】
◆日本
■【松本清張】
■【高村薫】
■【森村誠一】
■【水上勉】
■【黒岩重吾】
■【有馬頼義】
■【宮部みゆき】
■【桐野夏生】
■【東野圭吾】
■倒叙ミステリー
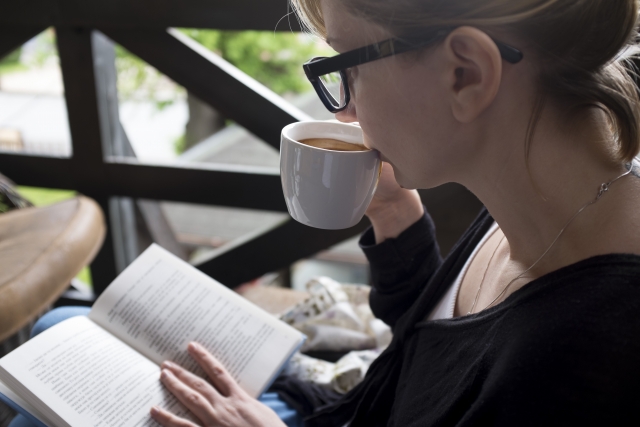
【代表的作家】
◆イギリス
■【F・W・クロフツ】
■【リチャード・ハル】
■【アントニー・バークリー(フランシス・アイルズ)】
◆アメリカ
◆日本
■【貴志祐介】
■【石持浅海】
■【岡嶋二人】
■【相沢沙呼】
■【大倉崇裕】
■【天野節子】
■【西尾維新】
■【井上真偽】
■【古野まほろ】
■【鯨統一郎】
■【深水黎一郎】
■【倉知淳】
■【夏樹静子】
■【松本清張】
■【我孫子武丸】
■メタミステリー/アンチミステリー

【代表的作家】
◆日本
■【竹本健治】
■【赤川次郎】
■【芦辺拓】
■【飛鳥部勝則】
■【綾辻行人】
■【鮎川哲也】
■【乾くるみ】
■【今邑彩】
■【歌野晶午】
■【折原一】
■【恩田陸】
■【笠井潔】
■【霞流一】
■【筒井康隆】
■【中井英夫】
■【東野圭吾】
■【舞城王太郎】
■【麻耶雄嵩】
■【三津田信三】
■【山口雅也】
■青春ミステリー/学園ミステリー

【代表的作家】
◆日本
■【樋口有介】
■【青崎有吾】
■【浅倉秋成】
■【天沢夏月】
■【如月新一】
■【貴志祐介】
■【河野裕】
■【柴村仁】
■【東川篤哉】
■【光原百合】
■【詠坂雄二】
■【米澤穂信】
■【恩田陸】
■【赤川次郎】
■【相沢沙呼】
■【辻村深月】
■【綾辻行人】
■【若竹七海】
■【法月綸太郎】
■トラベルミステリー/旅情ミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
◆日本
■【松本清張】
■【西村京太郎】
■【山村美紗】
■【鮎川哲也】
■【内田康夫】
■【赤川次郎】
■【梓林太郎】
■【有栖川有栖】
■【恩田陸】
■【木谷恭介】
■【島田荘司】
■【津村秀介】
■【豊田巧】
■【柴田よしき】
■法廷ミステリー/リーガルミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
◆アメリカ
■【E・S・ガードナー】
■【ディクスン・カー(カーター・ディクスン)】
◆ドイツ
◆日本
■【和久峻三】
■【大岡昇平】
■【高野和明】
■【柚月裕子】
■【宮部みゆき】
■【芦辺拓】
■【姉小路祐】
■【折原一】
■【加茂隆康】
■【小泉喜美子】
■【小杉健治】
■【佐々木譲】
■【師走トオル】
■【高木彬光】
■【中嶋博行】
■【中山七里】
■【夏樹静子】
■【法坂一広】
■【松本清張】
■警察ミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
■【ジョイス・ポーター】
■【F・W・クロフツ】
■【M・W・クレイヴン】
■【コリン・デクスター】
◆アメリカ
◆フランス
◆デンマーク
◆日本
■【西村京太郎】
■【山村美紗】
■【相場英雄】
■【我孫子武丸】
■【逢坂剛】
■【大倉崇裕】
■【大沢在昌】
■【香納諒一】
■【鏑木蓮】
■【今野敏】
■【佐々木譲】
■【雫井脩介】
■【柴田よしき】
■【中山七里】
■【貫井徳郎】
■【乃南アサ】
■【誉田哲也】
■【柚月裕子】
■【横山秀夫】
■【東野圭吾】
■【長岡弘樹】
■【米澤穂信】
■【秦建日子】
■【堂場瞬一】
■【川瀬七緒】
■【麻見和史】
■【濱嘉之】
■【富樫倫太郎】
■【島田一男】
■【藤原審爾】
■【結城昌治】
■【川崎草志】
■【髙村薫】
■【真保裕一】
■【松嶋智左】
■【小路幸也】
■【黒川博行】
■【折原一】
■【平石貴樹】
■【月村了衛】
■歴史ミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
■【ジョセフィン・ティ】
■【アビール・ムカジー】
■【ヴァシーム・カーン】
■【イーアン・ペアーズ】
■【デヴィッド・ヤング】
■【トム・ロブ・スミス】
■【アリアナ・フランクリン】
■【フィリップ・カー】
■【アレックス・リーヴ】
■【ローレンス・ノーフォーク】
◆アメリカ
■【ダン・ブラウン】
■【ジェイソン・グッドウィン】
■【ケイト・クイン】
■【ジェイムズ・ケストレル】
■【ジョージ・ドーズ・グリーン】
◆イタリア
◆スペイン
◆トルコ
◆日本
■【高田崇史】
■【高橋克彦】
■【井沢元彦】
■【芦辺拓】
■【鯨統一郎】
■【北森鴻】
■【浅倉卓弥】
■【高木彬光】
■【長尾誠夫】
■【中薗英助】
■【中津文彦】
■【斎藤栄】
■【山田風太郎】
■【典厩五郎】
■【加藤廣】

■ホラーミステリー

【代表的作家】
◆日本
■【綾辻行人】
■【三津田信三】
■【京極夏彦】
■【恒川光太郎】
■【貴志祐介】
■【我孫子武丸】
■【桐野夏生】
■【飛鳥部勝則】
■【井上夢人】
■【五十嵐貴久】
■【今村昌弘】
■【歌野晶午】
■【小川勝己】
■【恩田陸】
■【河合莞爾】
■【澤村伊智】
■【白井智之】
■【鈴木光司】
■【内藤了】
■【中山七里】
■【西澤保彦】
■【二宮敦人】
■【藤木稟】
■【誉田哲也】
■【前川裕】
■スパイミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
■【イアン・フレミング】
■【ギャビン・ライアル】
■【ジョン・ル・カレ】
■【フレデリック・フォーサイス】
■【ロバート・アースキン・チルダーズ】
■【ジョン・バカン】
■【サマセット・モーム】
■【グレアム・グリーン】
■【レン・デイトン】
■【デズモンド・コーリイ】
■【アガサ・クリスティ】
■【ケン・フォレット】
■【アダム・ホール】
■【ジョゼフ・ホーン】
■【クレイグ・トーマス】
■【アンソニー・ホロヴィッツ】
■【アーサー・コナン・ドイル】
■【バロネス・オルツィ】
■【ジョン・ガードナー】
■【クリストファー・ウッド】
◆アメリカ
■【エヴェレット・ハワード・ハント】
■【ドナルド・ハミルトン】
■【ロバート・ラドラム】
■【チャールズ・マッキャリー】
■【トム・クランシー】
◆フランス
◆日本
■【柳広司】
■【高村薫】
■【五條瑛】
■【野沢尚】
■【吉田修一】
■【結城昌治】
■【麻生幾】
■【西村京太郎】
■【深町秋生】
■【吉川英梨】
■サスペンスミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
◆日本
■【西村京太郎】
■【山村美紗】
■【宮部みゆき】
■【東野圭吾】
■【綾辻行人】
■【島田荘司】
■【横溝正史】
■【松本清張】
■【米澤穂信】
■【湊かなえ】
■【京極夏彦】
■【筒井康隆】
■【赤川次郎】
■【伊坂幸太郎】
■冒険ミステリー/怪盗ミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
■【ギャビン・ライアル】
■【ディック・フランシス】
■【E・W・ホーナング】
◆アメリカ
■【フレデリック・I・アンダースン】
■【トマス・W・ハンシュー】
■【E・S・ガードナー】
■【エドワード・D・ホック】
■【ヘンリー・スレッサー】
◆フランス
◆日本
■【江戸川乱歩】
■【芦辺拓】
■【二階堂黎人】
■【法月綸太郎】
■【神永学】

■SFミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
◆アメリカ
■【アイザック・アシモフ】
■【ジェリー・ユルスマン】
■【オースン・スコット・カード】
■【アルフレッド・ベスター】
■【ラリー・ニーヴン】
■【ジョン・ヴァーリイ】
■【ディクスン・カー(カーター・ディクスン)】
◆日本
■【森博嗣】
■【山口雅也】
■【宮部みゆき】
■【乾くるみ】
■【海野十三】
■【有栖川有栖】
■【二階堂黎人】
■【芦辺拓】
■【石持浅海】
■【西澤保彦】
■【田中啓文】
■【荒巻義雄】
■【岡嶋二人】
■【貴志祐介】
■【東野圭吾】
■【夢野久作】
■【鏡明】
■【都筑道夫】
■【法条遥】
■【山田宗樹】
■【筒井康隆】
■【赤川次郎】
■【綾崎隼】
■【井上夢人】
■【河合莞爾】
■【北村薫】
■【谺健二】
■【小林泰三】
■【沢木まひろ】
■【柴田よしき】
■【小松左京】
■【星新一】
■【柄刀一】
■【谷川流】
■【貫井徳郎】
■日常ミステリー/コージーミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
◆アメリカ
◆日本
■【北村薫】
■【加納朋子】
■【光原百合】
■【三上延】
■【相沢沙呼】
■【青井夏海】
■【我孫子武丸】
■【大倉崇裕】
■【大崎梢】
■【北森鴻】
■【倉知淳】
■【坂木司】
■【澤木喬】
■【田中啓文】
■【戸板康二】
■【似鳥鶏】
■【初野晴】
■【はやみねかおる】
■【東野圭吾】
■【松尾由美】
■【水原佐保】
■【森谷明子】
■【米澤穂信】
■【若竹七海】
■【蒼井上鷹】
■【青崎有吾】
■【碧野圭】
■【阿部暁子】
■【天祢涼】
■【伊坂幸太郎】
■【石持浅海】
■【乾くるみ】
■【岡崎琢磨】
■【如月新一】
■【近藤史恵】
■【佐藤青南】
■【篠田真由美】
■【柴村仁】
■【十階堂一系】
■【関口尚】
■【友井羊】
■【七河迦南】
■【長沢樹】
■【樋口有介】
■【麻耶雄嵩】

■ユーモアミステリー/バカミス
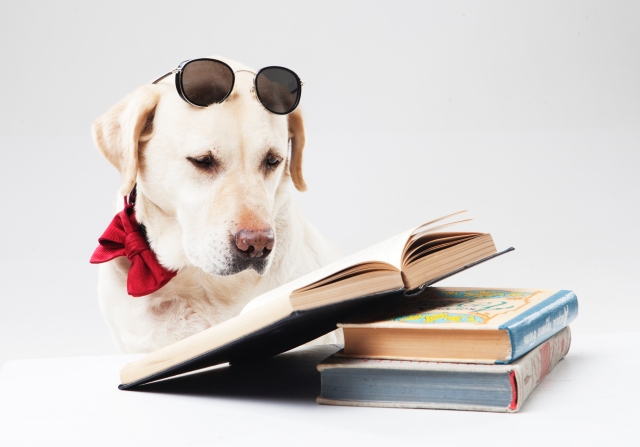
【代表的作家】
◆イギリス
◆アメリカ
◆日本
■【泡坂妻夫】
■【東川篤哉】
■【我孫子武丸】
■【伊坂幸太郎】
■【井上夢人】
■【大倉崇裕】
■【奥泉光】
■【折原一】
■【関口暁人】
■【天藤真】
■【富樫倫太郎】
■【七尾与史】
■【西澤保彦】
■【似鳥鶏】
■【貫井徳郎】
■【東野圭吾】
■【藤崎翔】
■【山田彩人】
■【横関大】
■【赤川次郎】
■医療ミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
◆アメリカ
◆日本
■【海堂尊】
■【久坂部羊】
■【仙川環】
■【帚木蓬生】
■【知念実希人】
■【岡井崇】
■【霧村悠康】
■【逢坂剛】
■【鏑木蓮】
■【岩木一麻】
■【大鐘稔彦】
■【里見清一】
■【中脇初枝】
■【桂修司】
■【松葉紳一郎】
■【南杏子】
■【河原れん】
■【太田靖之】
■【貫井徳郎】
■【浅ノ宮遼】
■【浦賀和宏】
■【下村敦史】
■【多島斗志之】
■【中山七里】
■【東野圭吾】

■グルメミステリー

【代表的作家】
◆イギリス
◆アメリカ
■【ダイアン・デヴィッドソン】
■【ナン・ライオンズ&アイヴァン・ライオンズ】
■【ジョアン・フルーク】
■【レックス・スタウト】
■【リリアン・J・ブラウン】
◆日本
■【近藤史恵】
■【柴田よしき】
■【友井羊】
■【北森鴻】
■【石持浅海】
■【太田忠司】
■【深緑野分】
■【相沢泉見】
■【斎藤千輪】
■【芦原すなお】
■【坂木司】
■【拓未司】
■【上田早夕里】
■【恩田陸】
■【宇江佐真理】
ミステリーをとことん楽しもう
ミステリーを読むには電子書籍が便利かも
BookLive!
「BookLive!」は、世界最大規模の総合印刷会社「凸版印刷」の系列会社が運営する「国内最大級」の「総合電子書籍ストア」で、100万冊以上ラインナップされ「全ジャンル」にわたり品揃えが豊富なことや、「入会時限定50%OFFクーポン」「1日1回クーポンガチャ」「LINE@クーポン」「まとめ買いptバック」などのほか、「ポイント還元」では「Tポイント」「クラブ三省堂ポイント」がもらえるなど、「クーポン」「キャンペーン」「ポイント還元」の充実ぶりは「ネットの口コミ」でも大好評!
「会員登録なし」で誰でも「無料で15000冊以上」の電子書籍を「まるごと1冊」読める「無料作品コーナー」や、「激安コーナー」「値引き作品コーナー」などでかなりお得に電子書籍を読めること、「作者のプロフィールや作品一覧」「レビュー」などが分かりやすく充実していることや、本棚アプリが使いやすく「本棚が使いやすい電子書籍ストアNo.1」にも選ばれたこともあるなど、人気が高く安心して利用できる使い勝手のよいサービスはとても魅力的です!
「さまざまなジャンルをいろいろ読みたい人」「『無料立ち読み』が好きな人」「本棚の『整理機能』や『サポート機能』などの使い勝手や読み心地にこだわりたい人」「『1日1回クーポンガチャ』などの充実したキャンペーンやクーポンが魅力的だと思う人」「『Tポイント』『クラブ三省堂ポイント』を利用する人」「できるだけ安く電子書籍が買いたい人」「本を選ぶときには作品一覧やレビューも必ず見るという人」には、非常におススメ!
BOOK☆WALKER
「BOOK☆WALKER」は、業界TOP3に入る大手出版社「KADOKAWA」が運営する「電子書籍ストア」で、運営会社の安全性は高く安心して利用でき、「全ジャンル」にわたって品揃えされていますが、「ライトノベル」では「KADOKAWA」は絶大な影響力があり、それがそのまま「BOOK☆WALKER」の大きな特徴になっているため、とくに「ライトノベル」「マンガ」「小説」「写真集」などの「エンタメ系のジャンル」には強みがあります。
会員登録をすると無料で自動適用される「ブックウォーカークラブ」という「会員ランク制度」があり、毎月の購入額でランク分けされて、ランクによって「電子書籍」を購入したときの「ポイント還元率」がアップしていきますし、ほかにも「初回購入金額の50%ポイント還元(上限なし)」「追加料金なしのオリジナル特典つき電子書籍の配信」「予約購入するだけで還元率アップ」「まる読み10分」などのキャンペーンも充実しているほか、スマホやタブレットのアプリも高機能で使いやすいと好評!
「ライトノベルが好きな人」「作者やイラストレーターによる『オリジナル描き下ろし』『ショートストーリー』『ドラマCD』などの『オリジナル特典つき電子書籍』が欲しい人」「ジャンルを問わず書籍を毎月一定額以上購入する人」「キャンペーンやポイント還元率は大切だと思う人」「『文庫・ライトノベル』『マンガ・雑誌』の読み放題プランに魅力を感じる人」「エンタメ系の本を中心に利用したい人」「KADOKAWA系の作品が好きな人」には、おススメ!
⇒豊富なラインナップで本をもっと快適に読もう! 【ブックライブ】
Kindle Store

「kindleストア」は、「Amazon」が運営する「総合電子書籍ストア」で、取り扱っている書籍の数は、他の電子書籍の販売サイトを圧倒的に上回る業界最高クラスであり「全ジャンル」に強く、中でも「ビジネス書」のジャンルが強みがあること、そして「検索性」に優れることや、30日間無料の「お試し期間」もあるなど、使い勝手も抜群!
電子書籍専用のリーダー端末「Kindle」は、紙の書籍に近い読み心地を実現しており使って損はないアイテムですし、「スマホ」や「タブレット」に「アプリ」をダウンロードすれば「Kindleストア」で購入した電子書籍を読めることや、また「Amazonプライム」に会員登録していると約1000冊程の書籍が無料で読め、さらに「定額読み放題サービス」である「kindle unlimited」の会員になると、120万冊以上もの本を好きなだけ読むことができるのも魅力的!
「本をたくさん読みたい人」「電子書籍専用リーダー端末『Kindle』を使いたい人」「Amazonの通販をよく利用している人」「読みたい本や欲しい本が決まっている人」「定額読み放題のKindle Unlimitedにとても魅力を感じる人」「ビジネス書を中心に本を購入したい人」には、特におススメ!
楽天Kobo
「楽天Kobo」は、「楽天」が運営する、「Kindleストア」に次ぐ業界シェアNo.2の安心安全な「電子書籍ストア」で、ジャンルや品揃えに関してはこの2つが業界最高レベルであり、ほとんどすべての「出版社」「ジャンル」の書籍と取り揃えていますが、特に「洋書」に関しては「kindleストア」をしのぐほどの品揃えで使い勝手もよく、また、専用リーダー「Kobo」でも「スマホ」や「タブレット」用の「アプリ」でも読むことができるのは便利です。
自分の好きな本だけを読むのなら、「ポイント」が使える「楽天kobo」の方が「kindleストア」よりもお得であり、「amazon」より「楽天」を使うことが多ければ、「楽天カード」などとの連携で「ポイント」がザクザク貯まるので、「キャンペーン」や「クーポン」「セール」などをうまく利用し、「ポイント」とあわせて使えば、かなり「おトク」にできますし、雑誌専門の「定額読み放題サービス」である「楽天マガジン」もあるのは魅力!
「楽天市場や楽天関連のサービスを普段よく利用する人」「楽天カードを持っている人」「割引きよりもポイント還元が好きな人」「電子書籍専用リーダー『Kobo』を使いたい人」「小説や洋書を中心に購入する予定の人」「楽天の『セール』や『キャンペーン』『クーポン』を利用したい人」「雑誌だけ読めればいいので『楽天マガジン』に魅力を感じる人」には、とくにおススメ!
ブック放題
「ブック放題」は、350種類以上の雑誌が読めるソフトバンク系の「雑誌読み放題サービス」で、「1ヶ月無料のお試し期間」があることや、「記事検索ができる」「複数端末が利用できる」、事前にダウンロードした雑誌をいつでも「スマホアプリを使って読める」ことなど、使い勝手がよいのはうれしいところ。
大きな特徴は、最新の「雑誌」だけでなく「マンガ」も読み放題で楽しめることで、マンガは旧作が中心ですが3万冊以上が揃っており、「懐かしの名作マンガ」が楽しめるのと、「旅行誌るるぶ」の取扱が他のサービスよりも圧倒的に豊富なので「旅行好き」には魅力的!
「月額料金が安い雑誌読み放題サービスを探している人」「なつかしいマンガが大好きな人」「旅行先で『るるぶ』が見たい人」「日常や旅先での暇つぶしに雑誌を読みたい人」「雑誌記事を検索したい人」「複数端末で利用したい人」には、おススメです!
この記事のまとめ
おもな内容のポイント整理
この記事のまとめ
- 「ミステリー」は日本で独自の大発展を遂げ、あらゆるジャンルと結びついてすそ野を広げた
- 様式性が強かったミステリーは、サブジャンルの幅を広げることでその閉塞感と停滞を乗り越えた
- 「本格ミステリー」「新本格ミステリー」などの「フーダニット」「ハウダニット」がその原点
- 「犯罪の社会的背景」「探偵の身分や環境」「事件の起こる場所」など様々な趣向のジャンルが生まれた
- ミステリーという形式は他のジャンルと融合させやすいため、今後も新しいサブジャンルがでてくるかも